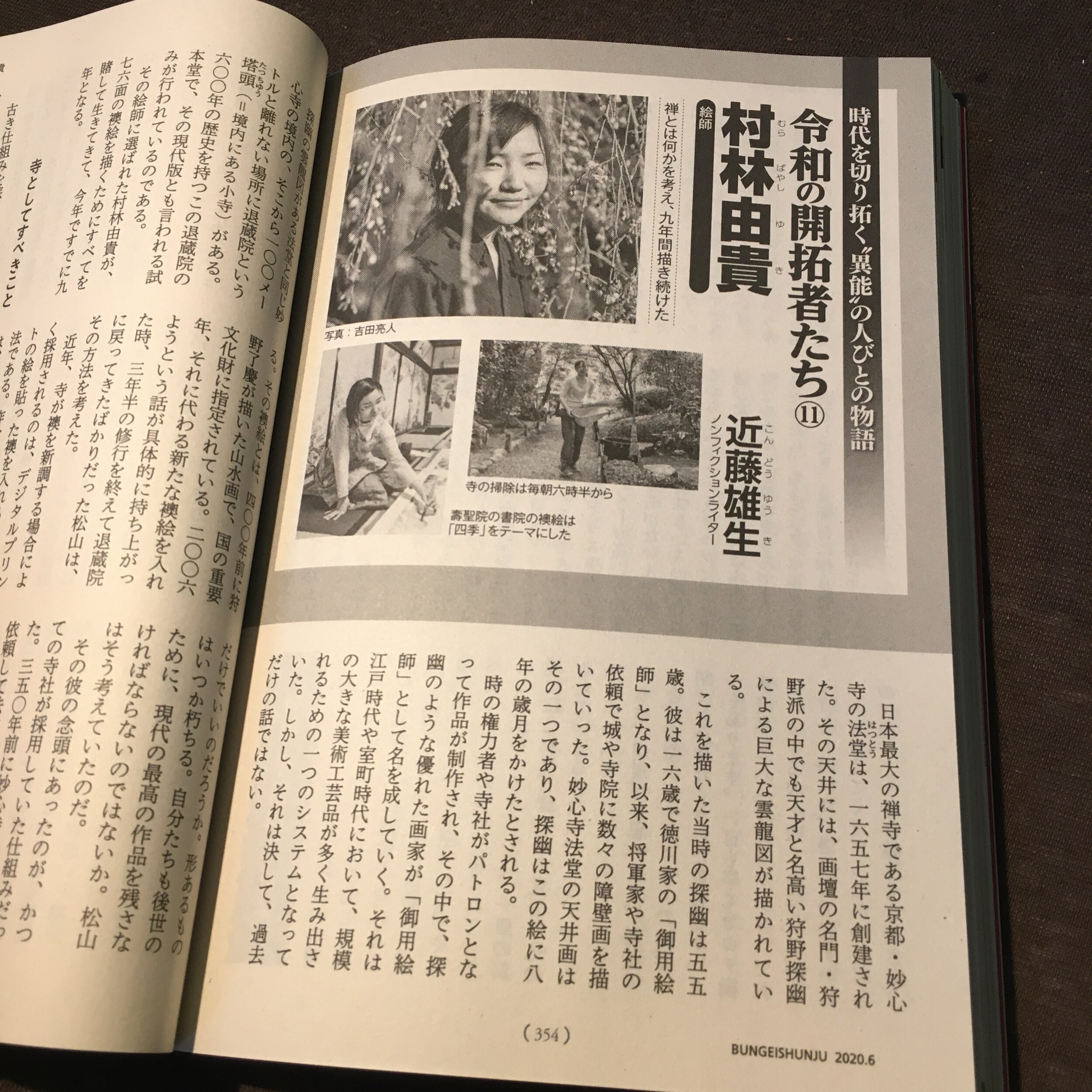(以下が追悼文です)
「永富さん、安らかに」 (近藤雄生、『季刊 中帰連』23号 2002年冬)
私は永富さんについてほとんど何も知らないといってもいいかもしれません。少なくとも永富さんにとって私は一介の若者以上のものではないはずです。そんな自分がここに永富さんの追悼文を書かせていただいて本当にいいものだろうかと、正直多少とまどいを覚えながらも、その機会をいただけたことを感謝しています。
私が永富さんのことを知ったのはほんの最近のことであり、お会いしたのも先の八月のある真夏日のたった数時間あまりでしかありません。永富さんの八六年に及ぶ人生の中に自分が多少なりとも直接的な関係を持つことが出来たのは、ドキュメンタリー映像を作るための取材でお会いした、そのほんのわずかな時間だけでした。しかしそれは、私にとってどれだけ長い時間に匹敵するか分からないほど貴重な出会いだったということを今、切に感じています。
そのころ私はもう一人の同年代の者とともに、生体解剖に関わった元軍医である湯浅謙さんの現在の活動を取材しており、そのときに湯浅さんから永富さんをご紹介いただきました。永富さんが近くの老人ホームにいらっしゃると聞いて、是非お会いしたいとお願いしました。「閻魔大王」と呼ばれていたほどの永富さんが今何を思いながら生活されているのか、私は聞いてみたいと思ったのです。
突然の訪問にもかかわらず快く私たちを迎え入れてくださった永富さんの、私たちへの最初の言葉は、「申し訳ありません、申し訳ありませんでした……」というものでした。背中を丸め、前かがみになりながら、しっかりと手を合わせて祈るようにそうおっしゃる姿を前に、私はなんと対応していいものか分からず、ただ沈黙し続けていたことを覚えています。
ただじっと聞いていることしかできない私たち若者に対して丁寧な言葉で接してくださるその姿からは、この人がそれほど残虐な行為を繰り返したなどということがどうしてもイメージできませんでした。しかし、そのギャップこそが現実だったのだと思います。永富さんの人生が半世紀以上前の話だけで説明されるものでは決してないという当然のことが、本人を目の前にして再確認できたような気がしたのです。特異な経験を経てきた人の人生は、その特異さだけで語られがちになりますが、もちろん実際にはその何倍もの、他の人と変わらぬ静かな日々が続いています。数々の残虐な行為と戦犯管理所での生活を経た後に、永富さんには四〇年ほどの時間がありました。私の会った永富さんはその全ての時間を内に抱えていたのです。それは、過去を見つめ、そして今自分が生きていることの意味を深く考える一人の老人の姿でした。
意識がない状態で同じ老人ホームに暮らしていらっしゃる奥様のことに話が及んだときに、永富さんのただならぬ思いはもっとも強く伝わってきました。
「生かされているというだけで…、ほんとうに幸せです…」
家内は「眼も見えない、口もきけない…、死んでるとおんなじ」です。しかし、生きている。その生きているという事実がいかに大きなことなのか…。「死んだらもうさわることもできない…」生きているからこそ、「毎日、いって、さわって、手を握って」やることができるんです…。「生きているということだけでも、ほんとうに幸せです…」
多くの人の命を自ら絶たせてしまった永富さんが、目を潤ませながらおっしゃったその言葉からは、他のどんな人にも表しえない重みと感慨が滲み出ていました。そのときの永富さんの涙は、奥様へと同じくらいに今生きている自分自身に、そして何よりも、彼が命を絶たせることになってしまった多くの人たちにへ注がれていたような気がします。
その涙は、いつしか取材を続ける私たちのもとへとつたってきました。
そしてその日から一ヶ月半ほどして、ドキュメンタリー映像は完成しました。
永富さんが亡くなられたのはその映像のテープを氏のおられた老人ホームに送ってから三週間ほどしてからのことです。テープが着いた頃にはすでに他の病院に入院されていたということを知らず、「永富さんはあれを見てどう思ったかな…」などとのどかに考えていた自分にとって、彼の死はあまりにも突然のことでした。
死の報告を受けたとき、永富さんのおっしゃっていたある言葉が頭をよぎりました。体が不自由になってはいるけど、特に病気もなく今を過ごしていることについて、
「私は死なせてもらえないのです。自分の罪をすべてこの世でぬぐいつくせるまで私はしぬことができないみたいなのです。…まだすべきことがたくさんある。そのためにこうして生かされているのではないかと思うんです…」
永富さんは「すべきこと」を終えることができたのだろうか…。それはしかし、私には分かるはずもありません。ただ、ちょうど偶然にも私たちがこの時期に映像を撮ることになったことが、もしかしたら死を迎える前の永富さんにとっての「すべきこと」に何らかの関係があったのか…そんな気がしないでもありません。私たちが作ったものが、少しでも永富さんが安らかに眠れず材料になればと願うばかりです。
(終)